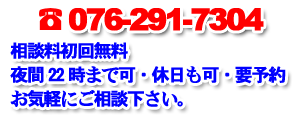高齢者問題 高齢者問題
子育てや仕事中心の生活を終え、いよいよ始まる自分のための時間。
多くの人々は、老後を自身の第二の人生として、充実させたいと望むものです。
その一方で、年を重ねていけば、誰もが体の不自由や、判断力の衰えを感じるようになります。
そんな自分の将来に、不安を感じる方も多いのではないでしょうか。今後一人になったら、
誰が自分を支えてくれるんだろう。身の回りの世話は?財産の管理は?
老後の暮らしに対する不安は尽きません。そこで高齢化社会が進む今、お年を召した方々を支える
様々な法律やサービスが登場していますが、後見制度や遺言書作成などは、
利用方法が分からない、手続が難しいのでは…戸惑う方も多いのではないでしょうか。
 解決のポイント 財産管理編 解決のポイント 財産管理編
高齢になると、次第に身の回りのことがわからなくなったり、認知症(痴呆症)になったりして、
苦労して築き上げた財産の管理をできなくなっていくことは避けられないものです。
現実にも悪徳商法等により高齢者が被害を受けてしまう事件等が後を絶ちません。
このような高齢者等判断能力が乏しい人の財産を守るために「成年後見制度」という法的制度があります。
成年後見制度には、次に述べるような任意後見制度と法定後見制度(後見・保佐・補助)があり、
本人が自分の身の回りのことや財産の管理をおこなう能力がどの程度あるかによって利用する制度が異なることになります。
 成年後見制度 成年後見制度
 任意後見制度 任意後見制度
 任意後見制度はどんな人が対象? 任意後見制度はどんな人が対象?
 まだ自分で身の回りのことや財産の管理を問題なくできる人です。 まだ自分で身の回りのことや財産の管理を問題なくできる人です。
 任意後見制度はどういう方法で利用するの? 任意後見制度はどういう方法で利用するの?

◆後見人:信頼できる人間を選びます。
◆効果が発生する時期: 実際に認知症などになって身の回りのことができなくなった、かつ任意後見監督人が選任された場合(選任は、予め又は後見人が家庭裁判所に選任申し立てします)
◆内容:財産管理等の事柄の処理
◆契約:「任意後見契約」 任意後見人としてあなたの代わりにやって欲しいというという契約
◆形式:公正証書
 任意後見契約で頼むことができる内容は? 任意後見契約で頼むことができる内容は?

◆電気・ガス・新聞の利用に関する契約や介護サービスなどの利用に関する契約
◆病院に入院する際の手続き等といった日常生活に関するもの
◆預貯金の管理、不動産の財産の売却・賃貸・修繕といった財産の管理に関するもの
※これらのほかにも任意後見人に頼む事柄は任意後見契約を結ぶときに自由に決めることができます。 ※ただし、任意後見契約は、任意後見人に頼める事柄は契約の締結などの法律行為に限られ、介護といった事実行為は含まれません。
 任意後見契約の効力はいつから? 任意後見契約の効力はいつから?
 任意後見人が任意後見契約に基づいてあなたの代わりに財産管理等をできるようになるのは、判断能力が実際に不十分となっただけではなく、任意後見人がしっかりと任意後見契約の内容どおりに事務を行っているかどうかを監督したり、状況を家庭裁判所に定期的に報告したりする「任意後見監督人」を家庭裁判所が選んだ時点からです。 任意後見人が任意後見契約に基づいてあなたの代わりに財産管理等をできるようになるのは、判断能力が実際に不十分となっただけではなく、任意後見人がしっかりと任意後見契約の内容どおりに事務を行っているかどうかを監督したり、状況を家庭裁判所に定期的に報告したりする「任意後見監督人」を家庭裁判所が選んだ時点からです。
▲トップ
 法定後見制度 法定後見制度
 後見 後見
 任意後見制度(後見)はどんな人が対象? 任意後見制度(後見)はどんな人が対象?
 既に日常の買い物すら自分ではできず、他の人に代わりにやってもらう必要がある人 既に日常の買い物すら自分ではできず、他の人に代わりにやってもらう必要がある人
 任意後見制度(後見)が開始するとどうなるの? 任意後見制度(後見)が開始するとどうなるの?

◆後見人は、売買契約などの財産に関する事柄だけでなく、介護サービス契約や介護保険の申請なども本人の代わりにできます。
◆本人も後見人も本人が自分で契約してしまった場合、その契約を取り消して、契約をなかったことにできます。 ただし、日用品の買い物など、日常生活に必要な事柄については取り消すことはできません。
 任意後見制度(後見)は誰が後見人になるの? 任意後見制度(後見)は誰が後見人になるの?
 特定の人・法人を後見人の候補として推薦することはできますが、最終的には、家庭裁判所が本人や親族の意見や状況を十分に検討した上で適任者を選びますので、推薦された人が必ず後見人になれるわけではありません。 特定の人・法人を後見人の候補として推薦することはできますが、最終的には、家庭裁判所が本人や親族の意見や状況を十分に検討した上で適任者を選びますので、推薦された人が必ず後見人になれるわけではありません。
 法定後見制度(後見)では、後見人は戸籍に載るの? 法定後見制度(後見)では、後見人は戸籍に載るの?
 後見制度を利用しても本人のプライバシー保護の観点から戸籍には記載されず、後見人登記制度という登記事項証明書の交付を受けられるのが本人・後見人等に限られている制度が利用されています。保佐・補助についても同様です。 後見制度を利用しても本人のプライバシー保護の観点から戸籍には記載されず、後見人登記制度という登記事項証明書の交付を受けられるのが本人・後見人等に限られている制度が利用されています。保佐・補助についても同様です。
 保佐 保佐
 法定後見制度(保佐)は、どんな人が対象? 法定後見制度(保佐)は、どんな人が対象?
 日常の買い物程度は自分でできるが、重要な取引(不動産や自動車の売買、借金等)をするには常に他の人の援助が必要な人です。 日常の買い物程度は自分でできるが、重要な取引(不動産や自動車の売買、借金等)をするには常に他の人の援助が必要な人です。
 法定後見制度(保佐)が開始するとどうなるの? 法定後見制度(保佐)が開始するとどうなるの?

◆a 一定の重要な取引を行なうためには保佐人の同意が必要になります。
例:不動産や自動車の売買、借金等
◆b 本人と保佐人は、本人がaに該当する行為を保佐人の同意なく行なった場合に取り消すことができます。
◆c 本人が同意すれば、a以外の行為についても保佐人の同意を必要としたり、特定の事柄について、本人の代わり保佐人にやってもらえるようにすることもできます。
 法定後見制度(保佐)では、誰が保佐人になるの? 法定後見制度(保佐)では、誰が保佐人になるの?
 最終的には家庭裁判所が適任者を選びます。 最終的には家庭裁判所が適任者を選びます。
※候補者を推薦することは可能です
 補助 補助
 法定後見制度(補助)は、どんな人が対象? 法定後見制度(補助)は、どんな人が対象?
 例えば軽度の認知症等で、不動産の売買といった重要な財産行為については一人でできるかどうか不安な人 例えば軽度の認知症等で、不動産の売買といった重要な財産行為については一人でできるかどうか不安な人
 法定後見制度(補助)が開始するとどうなるの? 法定後見制度(補助)が開始するとどうなるの?
 補助の場合、申立の範囲内で援助の対象となる不動産の売買等「特定の法律行為」を定めて、家庭裁判所から補助人に対して同意権や代理権を付与してもらうことになります。
補助人に同意権が与えられた事柄について、本人がうっかりと補助人の同意がないまま契約などをしてしまった場合には、本人も補助人も契約を取り消して、契約をなかったことにできます。
また、補助人に代理権が与えられると、補助人は代理権が与えられた事柄については、本人に代わって契約を結ぶこと等もできます。 なお、この補助制度を利用するためには、本人の同意が必要となりますので、本人の意思に反してこの制度が利用されることはありません。 補助の場合、申立の範囲内で援助の対象となる不動産の売買等「特定の法律行為」を定めて、家庭裁判所から補助人に対して同意権や代理権を付与してもらうことになります。
補助人に同意権が与えられた事柄について、本人がうっかりと補助人の同意がないまま契約などをしてしまった場合には、本人も補助人も契約を取り消して、契約をなかったことにできます。
また、補助人に代理権が与えられると、補助人は代理権が与えられた事柄については、本人に代わって契約を結ぶこと等もできます。 なお、この補助制度を利用するためには、本人の同意が必要となりますので、本人の意思に反してこの制度が利用されることはありません。
 法定後見制度(補助)では、誰が補助人になるの? 法定後見制度(補助)では、誰が補助人になるの?
 補助人についても後見人・保佐人と同様に候補者を推薦することはできますが、最終的には家庭裁判所が適任者を選ぶことになります。 補助人についても後見人・保佐人と同様に候補者を推薦することはできますが、最終的には家庭裁判所が適任者を選ぶことになります。
▲トップ
法定後見制度概要
後見制度
| 対象 |
事理弁識能力を欠く常況にある人 |
| 申立権者 |
本人、配偶者、4親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人、検察官、市区町村長 |
| 成年後見人の権限 |
本人の財産について全面的な管理権・代理権。 「日常生活に関する行為」を除くすべての行為についての取消権。 |
保佐制度
| 対象 |
事理弁識能力が著しく不十分な人 |
| 申立権者 |
本人、配偶者、4親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人、検察官、市区町村長 |
| 成年後見人の権限 |
民法所定の重要な取引行為に関する同意権・取消権を有する。申立てにより家庭裁判所は代理権を付与することもできるが、代理権の付与には本人の同意が必要。 |
補助制度
| 対象 |
事理弁識能力が不十分な人 |
| 申立権者 |
本人、配偶者、4親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、検察官、市区町村長 |
| 成年後見人の権限 |
家庭裁判所に対する同意権付与の審判により付与された特定の法律行為に関する同意権・取消権。
※本人の同意が必要。 |
|